エルニーニョ&ラニーニャ
他方、「女の子」を意味するラニーニャはエルニーニョとは反対の現象です。赤道の東風が強まって、中・東部赤道太平洋の海面水温は平年よりも下がるため、大気循環場にも影響を与えます。また、エルニーニョほどではありませんが、ラニーニャも異常気象を起こすことで知られています。
| エルニーニョ年、ラニーニャ年、通常年の大気・海洋相互作用の概念図 | |
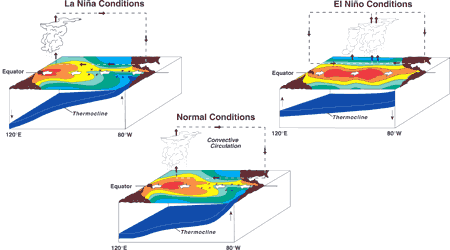 |
|
| オーストラリアと南米の間の熱帯太平洋域について、海面水温、赤道上の温度躍層の深さ、貿易風の偏差、対流活動と大気循環の分布を示しています。中央:通常年。南米沿岸で貿易風によって冷たい海水の湧昇が起こっているため、太平洋の東側の海面水温は西側に比べて低くなります。左:ラニーニャ年。太平洋の東側で温度躍層の深さが浅くなり、海面水温が低くなります。逆に西側で温度躍層が深くなり、海面水温の高い領域と対流の中心位置が西側にシフトします。右:エルニーニョ年。貿易風が弱まるため、南米沿岸での冷たい海水の湧昇が減少します。結果として海面水温の高い領域が赤道上に東へ拡がり、対流の中心も中部熱帯太平洋に移動します。 画像提供:米国大気海洋庁(NOAA)太平洋海洋環境研究所(PMEL)Tropical Atmosphere-Ocean(TAO)プロジェクト・オフィス、Dr. Michael J. McPhaden。 |