観測の概念
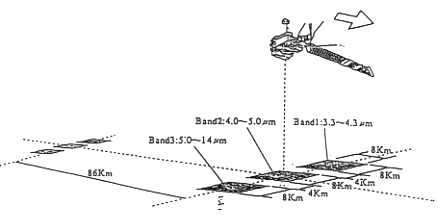
|
| 温室効果気体センサ(IMG)観測の概念図 |
温室効果気体センサ(IMG)は地球の熱放射収支、大気温度の垂直分布、地表温度、雲の物理的特性を監視、研究するためのセンサです。IMGは通商産業省の委託により(財)資源探査用観測システム研究開発機構が開発したものです。
IMGは地表及び大気からの赤外放射のスペクトルを高精度に測定することができます。IMGによって得られた高精度のデータによって、水蒸気の濃度や、他の温室効果気体の量を推定できます。
大気中の微量成分気体、例えば二酸化炭素、メタン、酸化窒素、フロン等の濃度増加は顕著であり、これらは人類の活動によって引き起こされています。しかし現状では、これら気体の人為的発生源の分布や発生量については限られた知識しかありません。発生量を把握しておくべき現象としては、化石燃料の燃焼や森林破壊があげられます。微量成分気体の濃度変化を観測することで、全地球規模で、または地域的に制限するべき気体がわかります。
さらに、微量成分気体の発生源やシンク・ストレングスは陸地や海域の生態系によって大きく違うこともあります。
IMGの主な特徴
| Spectral Range of Measurement | 714-303 cm (14 - 3.3um) |
|---|---|
| Wave number resolution | 0.1cm (apodized) |
| Absolute accuracy of measurement | < = 1k |
| Stability of measurement | <= 0.1k |
| Interferogram scan time | <= 10sec |
| Sampling per intergerogram | <= 100,000 |
| Mass | < 115kg |
| Power consumption | < 150w |
| Approximate Size | within 1000x800x500mm |
IMGはマイケルソン干渉計を用いたフーリエ変換赤外分光計で二つのミラーとビームスプリッタが付いています。放射光はビームスプリッタにより2つの光路に分割され、ミラーにより反射されていずれも検知器に向かいます。この時片方の鏡を光軸に平行に移動させると光路長の変化により検知器上の光の強度が変動します。この変動を測定したデータはインターフェログラムと呼ばれ、入射光をフーリエ変換したものです。従って得られたデータを逆フーリエ変換することにより入射光スペクトルが得られます。光学系の口径は高いS/N比を得るため10cmとなっています。移動鏡は磁気ベアリングで保持され、リニアモータにより10cmの距離を10秒間で移動します。
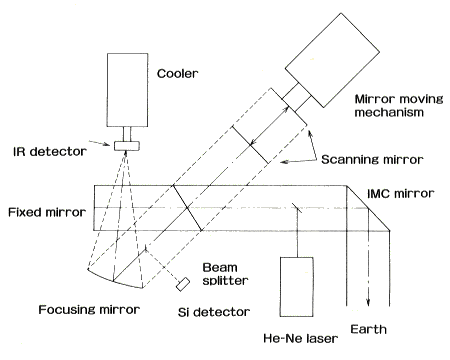
|
| 温室効果気体センサ(IMG)光学システム図 |
